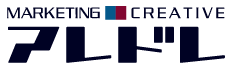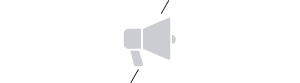仕事を休む? 休まない? 使いづらい生理休暇 どう使えるようにする?

働く女性の約9割が毎月の生理痛やさまざまな体調不良を抱えています。 男女平等社会の中、女性が生理の体調不良を押し殺して働き続けることのないように、重い生理痛のある人は、法律で認められている「生理休暇」を申請して会社を休む権利があります。女性であれば誰でも取得できる権利です。
しかし、生理休暇を取りたいと思っても様々な理由からなかなか言い出しにくいのが現状のようです。 多くの女性達は生理休暇をどうとらえているのでしょうか?
女性が働きやすい環境を整えることは、会社にとってもプラスになります。 上司として会社として、生理休暇の取得をどうしたら円滑に進められるのか。 生理休暇をとりやすくする実際の会社運営の取り組みはどんなことでしょう。
生理休暇についてさまざまな面から考えてみます。
生理休暇とは?

労働基準法第68条では、生理休暇が認められています。 「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」の中で、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」とあります。
女性が生理休暇を申し出た場合、会社はそれを却下することはできません。 生理休暇を利用するのは、従業員の妥当な権利です。
また「生理日の就業が著しく困難な女性」とありますが、それを証明するような医師の診断書などをわざわざ取得して提出する必要はありません。
また、人によって生理痛の期間や重さが違うため、生理休暇を取得できる日数というものは特に法で定められていません。 実際に取得する場合は、常識の範囲内でというのが望ましいと言えるでしょう。
生理休暇が有給になるのか無給になるのかは会社側と労働者との取り決めで定めることができます。 生理休暇を取る場合は、事前に有給無給を就業規則などできちんと確認することです。
会社としては重要なポイントが4つあります

- 特別な証明(医師の診断書)がなくてもよく、同僚の証言程度でも実践する必要がある (昭和23.5.5 基発682号、昭和63.3.14 婦発47号)
- 生理休暇の日数を制限することは出来ず、半日や時間単位で取得が可能である (昭和61.3.20 基発151号、昭和63.3.14 基発150号)
- 賃金の取扱いについては労使の取決めによって決まるため、制度上無給とすることは可能である (就業規則の変更は可能、昭和23.6.11 基発1898号、タケダシステムズ事件最高裁昭和58.11.25
- 社員が生理休暇を請求して取得させなかった場合には、30万円以下の罰金がある
この4つのポイントは、生理休暇を考える上で重要なポイントになります。
生理休暇 実際の取得率は?

しかし、生理休暇を取る人は実際は減っています。
厚生労働省が全国約6,000事業所を対象に行った調査では、生理休暇を取得した従業員は 1997年度は3.3%、 2003年度は1.6%、 2014年度は0.9%。 取得率は減っていて、いまも取得率は低いままだということです。
また先にも書いた通り、生理休暇中の賃金を有りにするか、無しにするかについての法律上の定めはなく、それぞれの企業が決めることになっていますが、一定の規模以上の事業所に対して行われた調査では、有給としている事業所 2009年度には42.8%の事業所が有給としていたが、2015年度は25.5%でしたので、こちらの割合も下がっています。
なぜ取得率がこれほど低くなったのでしょうか?なぜ有給としている事業所も減っているのでしょうか? そこにはいろいろな側面があるようです。
なぜとらない?…生理休暇は自分も周囲も取らないのが常識?

女性向けWEBメディアオズモールのアンケートによると、職場環境として取りづらいと答えた人が8割。 取ったことのない人も8割。
取得率が低い最大の原因は、やはり心理的な抵抗感にあるといえるかもしれません。
生理は恥ずかしいものとして見られてしまいがちです。 休暇を利用するには申請が必要ですが、冒頭の調査結果を見ても、自ら申請するハードルは高いといえるでしょう。
また、生理の不調は個人差が大きく、寝込んでしまう重い人から、普通に生活できるくらい軽い症状の人もいます。 そのため、男性だけでなく、実は同性である女性社員からも理解されにくい場合があります。
厚生労働省雇用機会均等課は、 「職場には生理のことは伝えず、年次有給休暇を使って休んでいるかもしれない。」 「人手不足の企業では、休みたくても休めない女性もいるかもしれない」と話します。
全労連の調査では、生理休暇をとっていない人に、とれない理由についても聞いています。
1番目は「人員の不足や仕事の多忙で職場の雰囲気としてとりにくい」 2番目は「苦痛ではないので必要ない」 3番目は「はずかしい、生理であることを知られたくない」 など様々な理由で取りづらい点も指摘されています。
生理休暇はずるいのか?

中には生理の不調を大義名分に使ったり、悪用する女性もいることは、会社にとってはデリケートで難しい問題といえます。
とある会社では、生理痛がかなりヒドイという従業員がおり、その痛みを抑えるために薬を処方してもらっているとのことで、薬の副作用もひどいらしく、薬を飲んだ後は人との対応や話し方も無気力・無礼になってしまい、ことにリーダー格の女性なので、会社の雰囲気にも多少の影響を与えるそうです。
生理痛が辛いことはわかりますが「生理痛がひどいから業務中も仕事が手に付かないのよ。遅刻するのよ。欠勤するのよ。何か文句ある?」 というような姿勢は許してはならないでしょう。
個人差の大きい事なので対応が難しいとは思いますが、職場の雰囲気、周囲のモチベーションや仕事への士気にも関わることなので、あまり目に余る場合は言いたい放題にさせておくのはよくないことです。
「女子社員の生理休暇取得を何とか邪魔(制限)できないものでしょうか? うちの職場の女子社員の中に、毎月必ず生理休暇を取る人が数名居ます。 しかも、仕事の締め切りが有る金曜日とか、資料提出をする月曜日に、彼女の休みが集中して、他の女子社員のヤル気にも悪影響を及ぼしています。」
こうしてごくまれにですが、周りの社員や上司、人事を困らせるような利用方法をする従業員がいるのも事実です。
生理休暇乱用従業員がいたら 人事としての観点から

生理休暇を悪用されないように、どのように対応するのが良いのか、 以下のまとめが例としてあります。
生理休暇乱用を防ぐ2つの対策
生理休暇は診断書の提出は不要ですが、生理が辛くて休んでいることが前提となります。
生理休暇を取得した上で、自分の都合(旅行など)のために使用し、判明した場合は、「就業が著しく困難であったとはいえない」として懲戒処分が認められたケースもあります(岩手県交通事件平成8)。
それでは、具体的にどのような対策を人事としては実施できるでしょうか。
- 就業規則の改正での無給化
- 生理休暇日の事情チェック
1.就業規則の改正をして生理休暇を無給にする
先に書いた通達や最高裁の見解があるように、就業規則を改正し、生理休暇を取る際には「無給」にすることが可能です。
-
- 当事者間の取決めに委ねられた問題であるため、生理休暇の取得を著しく抑制しない限りは労働基準法上違法ではないとしています(エヌ・ビー・シー事件)。
-
- 生理休暇の取得日を昇給・昇格の要件として出勤率の算定にあたり欠勤日扱いにすることは、無効であるとしています(日本シェーリング事件)。
-
- 一般の私傷病と同様、このような生理休暇を利用したことで一律に業務を評価しないで賞与の不支給や昇給停止を行うことは問題なのであって、結果としてパフォーマンスが低いということを理由とする場合は違法とされません(学校法人東邦学園事件)。
- 有給の生理休暇を年24日から月2日に変更し、有給率も100%から68%に変更することは様々な配慮及び濫用状況を考えて、合理性があり、改正規則は有効とされています(タケダシステム事件)。
以上のような就業規則の整備については、社会保険労務士や弁護士等、専門家と相談して整備をするのが望ましいでしょう。
2.生理休暇日の事情チェック
就業規則を変更せずに当人の事情をチェックして、乱用を抑止する方法もあります。
例えば、生理休暇の申請書に添付する資料を2点追加します。
- 本人から生理時の体調不良によって具体的にどのような影響が業務上発生しているのかを記載してもらう。(就業可否の状況の確認)
- 診断書は不要で同僚の証言程度で良いことから、上司や先輩同僚の女子社員からも証明書を記載してもらう。
という運用を義務付けて、このような手続きなしの生理休暇の申請は、年休としての振替にしない限りは欠勤として対処すること申し渡し、実行する。
さらに乱用していることが目される従業員には、休暇中に電話して在宅と静養を確認する方法も考えられますが、上記のような対応ができるにせよ、生理の重さによって就業が著しく困難な状況も実際多々あるのだという認識は忘れないようにしたいところです。
また別の大切なアプローチとして、強い痛み等によって業務遂行ができないと想定される場合、婦人科受診を勧めることが重要です。生理不調のガマンが重病を招く恐れもあります。
生理時の仕事量を調整したところ、仕事がスムーズにまわるようになったケースも

「生理痛は心臓発作と同じくらい酷くなることもある」というのが「Independent」が報じた「University College London」の研究結果で、「生理痛は風邪の日に生産性が落ちてしまうのと同じくらい、仕事に影響を及ぼす可能性がある」という研究発表もあります。
腹痛、貧血や下痢、吐き気、頭痛などが生理にはつきもので、外回りや緊張するプレゼンや難しいお客様の対応に走り回るには、難しい体調です。
生理がつらいのに働くのは非効率
女性の社会進出が進んでいるなかで、生理休暇に対して理解のある会社も増えてきました。 また、女性社員の割合が多い会社などでは生理休暇を有給にし、申し出やすいようにしているところもあります。
生理休暇を推進し、環境改善やコミュニケーション改善で働き方の変革を進めていこうという新興企業の動きがあります。
ネット事業を手がける「サイバーエージェント」(東京)は14年、独自の休暇制度「エフ休」を設けました。名称は英語で女性を表す「female」の頭文字から取ったそうです。 生理休暇や婦人科の受診、不妊治療による休暇などを取る際、全て「エフ休」と上司に伝えて休むことができる。 同社の女性(30)は「男性上司には生理とは言いにくいので助かる」と話します。
恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」を運営する株式会社エウレカ(東京・南青山)は、社員数人で大量の仕事を回していた2008年の創業時から生理休暇制度を取り入れてきたということです。
「生理がつらいのに働くのは非効率」という合理的な判断から、「部下の生理前や生理中の仕事の量を調整したところ、仕事がスムーズにまわるようになった」(共同創業者・取締役COO 西川順さん談:ハフポスト取材)
生理中でもそれぞれの判断に基づいて働けるオフィス環境も整えている。 一連の環境整備が、生理痛を抱える女性だけでなく、企業内全体のダイバーシティ推進にも役立っていると指摘しています。
生理休暇をとりやすくする実際の会社運営の取り組みは?

従業員が働きやすさを感じることには、賃金、労働時間、待遇、福利厚生、評価制度、人材教育制度など様々にあるでしょうが、中に大きく休暇についても働きやすさの条件の一つにあげられるでしょう。
休暇の取りやすい職場の環境は、計画的な取得の管理が職場に根付いていることが大きな要素です。 たとえ生理休暇が就業規則に盛り込まれていたとしても、誰もが申請しづらく形骸化していたのでは無意味です。
人手不足や忙しさから、長時間労働が常態化していたり、有休が取れても5割そこそこくらいだったとしたら、生理休暇を希望する側も受ける側も、さまざまな理由から摩擦を感じることもあるでしょう。
会社としては、生理休暇で休んだ女性が抜けた作業をフォローする必要があります。 実務レベルで負担なくスムーズな業務を遂行するのに、時短を計画的に進めるためのプログラムがあることが理想です。
日頃からの時間外労働の削減、所定労働時間の短縮を徹底的にやらないと、休暇の日数増の取得促進につながりません。
長期の業務計画の上に、各人の休暇取得を目算し、確実な休暇取得を図りつつ、仕事を計画的・効率的に進める風土を職場に定着させる。
ポイントは業務計画と各人の休暇をしっかり可視化して、上司や周りのメンバーは、業務分担やフォローなど、どのような体制づくりが必要か、何をすべきかを確認して実行することです。
大胆かつ抜本的な改革ですが、実際的な導入には、職場ごとに生理休暇を年間ベース・あるいは月ベースで、女性従業員から希望日を申請させて休暇計画を立て、全員分を人事部門に提出するよう義務付けるなどがあっていいかもしれません。
そして、上司に休暇を「取らせなければいけないもの」という認識が浸透していなければならないでしょう。 人事から取得促進の働きかけを行うことが必要なケースがあるかもしれません。
仕事は増えていき、より複雑化していくものでしょうが、増えていくものに対していつまでも同じやり方をしていては通用しません。 どうやって生産性を高めていくか、時間を短縮していくか、という発想と取り組みが不可欠です。
それを突き詰めてやっていくだけでは身体や健康維持が持たなくなりますから、効率的に仕事を進めるためにも、ある程度の休暇は必要です。 休むときは思い切って休む。逆にやるべきときは極端な話、徹底して完遂するくらいに働く。集中したハードワークと休暇のメリハリが働き方としてあるべき姿です。
女性従業員は、どうすれば自らの生理休暇を取りやすくすればいいか?

そして、休みを取る当事者の意識が大事なのは勿論です。 女性従業員が休暇を取得しやすくなるためには自らの働きかけも重要なのです。
休暇を取る側は生理中に休めるよう、どう仕事をこなしていけばよいかをしっかり考えて実行すること。
- まずは日頃から与えられた仕事をきちんとこなし
- 周囲の信頼を得る
- そして自ら周りに理解してもらうために、同僚や部下や上司とコミュニケーションをとり良好な関係を築くことが大事
その上で、休暇の間、自分がいなくても業務が回る状態になるよう、準備を進めておくことも重要です。
生理休暇は労働基準法で認められている女性の権利

万人が生理痛を理解することは難しく、女性が生理休暇の申し出をすることに対し、今の日本社会では理解されないことが多いかもしれません。 しかし、生理休暇は労働基準法で認められた権利なので、倒れるほどの痛みをガマンして出社するのではなく、必要であれば取得して、ゆっくりと体を休ませるようにしましょう。
女性が社会で活躍を始めている中、多くの女性が生理に関する悩みを押し殺して働き続けるのが、健全な社会でしょうか。
自分の隣に座る仲間、仕事のパートナー、会社を支えてくれている従業員が青ざめた顔で我慢し続けるのを見過ごす社会・会社であってほしくはない。 可能な範囲で解決策を考えていこうとする社会であって欲しいと願います。